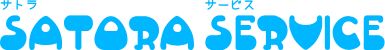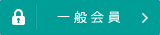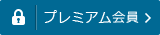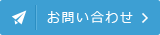TOPICS
腹部のアセスメント
こんにちは 😀 本日は腹部のアセスメントについてお話ししていきたいと思います ❕
腹部は呼吸や循環と違い、数値で見えにくい部分なので、フィジカルアセスメントがより重要になってきます。
腹部の診察のみ、「視診→聴診→打診→触診」と、順番が決まっています。
所見が変わってしまう恐れがあるので、「触る前に聴く」というのがポイントです。
1. 視診
発赤や発疹といった一般的な視診に加えて、腹部膨満と手術創、鼠径部、静脈瘤を確認するのがポイントです。
腹部膨満は腹水や腸閉塞、腹部大動脈瘤を示唆します。腹囲測定をするときは、臍の上と最も膨満しているところを測定します。
手術創は、その創に関連した臓器やなんらかの手が加えられている可能性があり、問診や身体診察の幅が広がるため、必ず確認します。
鼠径ヘルニアは、鼠径部のヘルニアですが、嵌頓すると腸閉塞へと進展します。鼠径部は意識して確認しないと見逃すため、腹部の診察においては鼠径部まで必ず確認します。
臍を中心に腹壁静脈が怒張している場合(メデューサの頭)は、門脈圧の亢進を疑い、鼠径部から上に怒張している場合は、下大静脈の閉塞を示唆します。
2.聴診
腸蠕動音の確認は、基本的に一箇所でOKです。
通常、腸蠕動音は5回/分程度です。炎症等により腸蠕動が活発になると蠕動音は亢進して聴取できます。また、イレウスにより蠕動が低下すると蠕動音は減弱、消失します。
「キーン」「カーン」と高い音は金属音と呼ばれ、聴取すると腸閉塞を示唆します。
聴診器を当て、腹部全体を揺らすことでぽちゃぽちゃと腸管内の液体の音が聴取できると、振水音と呼ばれ、腸管内に液体あるいは気体が貯留している所見であり、腸閉塞を示唆します。
3.打診
患者さんに仰臥位になってもらい、膝を曲げた状態で行います。鼓音が聴取できれば、消化管ガスの貯留、腸閉塞、消化管穿孔などを示唆します。濁音であった場合は、肝臓等の実質臓器あるいは腫瘤、腹水を示唆します。鼓音はポンポンと高い音、濁音は低い音です。
4.触診
仰臥位で膝を曲げてもらいます。痛みを訴えている場合は、痛みのない場所から触診をはじめ、痛い場所は最後とします。疼痛がある場合、あるいは腹膜炎を疑っている場合は、腹膜刺激徴候を確認します。
腹膜刺激徴候は、腹膜を引っ張って痛みが誘発されるかを確認します。代表的なものに反跳痛(ブルンベルグ徴候、リバウンド)や筋性防御があります。反跳痛は押した時より、離した時の方が痛ければ陽性です。筋性防御は腹部が板のように硬直することです。腹膜炎は見逃すと生命の危機に陥る恐れがあるため、すぐに医師に報告する必要があります。
腹部のアセスメントは実際に経験した方が覚えやすいです。
臨床に出たら、実践の中で覚えていけるといいと思います。
ではまた 🖐️