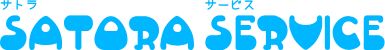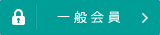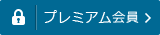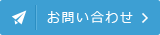TOPICS
問診
こんにちは!
ちょっと気を抜いていたら久しぶりの更新しなってしまいました 😱
ここから、気を引き締めなおして更新して行こうと思います 😃
さて、皆さん、問診をしたことがありますか?実習のなかでは経験できないかもですね。でも、患者として問診票を書いたことはあると思います。
診断に必要な情報の7〜8割は問診で得ることができると言われています。
本日はその問診の方法についてお話ししたいと思います。
①主訴
まず現在の症状を確認します。例えば胸が苦しい、吐き気がする、眩暈がする等です。
②現病歴
はじめは「どうしたのか」と開放型質問(Open-ended Question)で尋ね、自由に話をしてもらいます。その結果、いくつかの疾患が頭に浮かぶと思うので、その疾患に合う症状、合わない症状の有無を確認し、閉鎖型質問(Closed Question)で答えてもらいます。その際、以下の「SAMPLER」、あるいは痛みが主訴の場合は、「OPQRST」を意識して症状を整理すると鑑別疾患を挙げやすくなります。
SAMPLER
Signs/Symptoms 徴候と症状
Allergy アレルギーの有無
Medication 内服薬、通院歴
Past medical history 既往歴
Last meal 最終食事
Event/Environment イベント、環境
Risk factor リスク因子
OPQRST
Onset 発症様式
Palliative/Provocative 増悪寛解因子
Quality/Quantity 性質
Region/Radiation 場所、放散痛
Associated Symptom 随伴症状
Time course 時間経過
③既往歴・併存症
既往歴は過去の治療歴、手術歴、薬剤使用歴、輸血歴、妊娠歴、出産歴、アレルギー歴等であり、その患者を理解する上で重要な項目です。
④家族歴
家族性の疾患や同様の症状を来している場合は感染症の鑑別に役立ちます。家族構成、特に両親や兄弟の病歴は重要です。
⑤患者背景
喫煙歴、飲酒歴、職業歴、運動習慣、海外渡航歴、性交渉歴等
上記のポイントを押さえながら問診を進めていきます。
問診を行うことで、患者に必要最低限の検査や治療を提供することに繋がります!
疾患をある程度類推できるよう知識を蓄えておくことももちろん重要ですね!
ではまた 🖐️